サディステックWAKAYAMA800 [鍋谷峠-紀の川フルーツライン-紀見峠]

服部産業のH本師匠にお誘いを受けたので、今週末も鍋谷峠に向かうことにした。H本師匠のご指導のお蔭で1年ぶりの自己記録更新を果たした先週に続いて今週もといきたいところだが、体調はもうひとつでアプローチから身体が重たく脚が回らない。心拍数もやや高い。
 国道170号線バイパスを越えて山麓が近付いてきたところで、サイクルショップカワハラダの剛さんに追いつかれ、走りながら二言三言。鍋谷峠に向かうとしばしばお会いするが、今日も鍋谷峠とのこと。「店開けなかんので」と、スパッと先行していかれた。
国道170号線バイパスを越えて山麓が近付いてきたところで、サイクルショップカワハラダの剛さんに追いつかれ、走りながら二言三言。鍋谷峠に向かうとしばしばお会いするが、今日も鍋谷峠とのこと。「店開けなかんので」と、スパッと先行していかれた。
 H本師匠はともかく、私は着いていける脚力がないので、自分のペースで先に進む。定点観測地点の父鬼集落の温度計は7:25の時点で19度を表示。数字上は先週より1度低いが、体感的にはすでにかなり暑い。これから先が思いやられる。
H本師匠はともかく、私は着いていける脚力がないので、自分のペースで先に進む。定点観測地点の父鬼集落の温度計は7:25の時点で19度を表示。数字上は先週より1度低いが、体感的にはすでにかなり暑い。これから先が思いやられる。
いつものごとく製材所前の鍋谷橋からアタック開始。調子が上がらないなりに心拍数を170~175bpmの範囲に収めることを意識して、今回はやや積極的にダンシングを使うようにした。序盤、中盤とこの目標はほぼ達成でき、体感的には少し余裕を感じるほど。しばしば心拍数が175bpmを越えてペースを抑制する展開が続く。
 先に上って引き返してきたカワハラダの剛さんとすれ違い、終盤は早めにスパートを掛けて最後は心拍数を今季最高の190bpmまで追い込んで8:15頃にゴール。
先に上って引き返してきたカワハラダの剛さんとすれ違い、終盤は早めにスパートを掛けて最後は心拍数を今季最高の190bpmまで追い込んで8:15頃にゴール。
一見、心拍とペースのコントロールは上手く行ったように思えたし、TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)の調子も悪くなかったが、タイムは26分28秒と先週より1分近く遅くなった。H本師匠によると序盤のペースが大幅に遅かったとのこと。序盤に慎重になり過ぎたことが主原因のようだが、全般を通じて体感的には余裕があった。心拍数値に囚われすぎて追い込みきれなかったのが、もうひとつの原因だ。今日は不調なりに、もうちょっと追い込んでも大丈夫だったのだろう。とは言え、これまでの経験で「体感」がアテにならないことも痛感している。ノリクラ本番は長丁場なので、コントロールはさらに難しい。客観的な数値が他にもあれば参考になるが、パワーメーターにはまだ手が出そうにない。
 今日は用事のあるので引き返すH本師匠とは、ここでお別れ。私は和歌山側に下った。暑くなりそうなのでためらいもあったが、回復力の向上のために、ロングライドにも取り組んでおきたい。
今日は用事のあるので引き返すH本師匠とは、ここでお別れ。私は和歌山側に下った。暑くなりそうなのでためらいもあったが、回復力の向上のために、ロングライドにも取り組んでおきたい。
旧道区間の平集落を見下ろす定点観測点。青空ながらも少し霞んだ夏らしい風景。もっとも湿度はそう高くないので湿気による霞というよりは、光化学スモッグなのだろう。
 道の駅くしがきの里に立ち寄って、今回もWAKAYAMA800のスタンプをゲット。期間中にリピーターポイントが貯まる10回も訪れる可能性は低いだろうが、通り道なので念のため。
道の駅くしがきの里に立ち寄って、今回もWAKAYAMA800のスタンプをゲット。期間中にリピーターポイントが貯まる10回も訪れる可能性は低いだろうが、通り道なので念のため。
 明日は仕事だし、どんどん気温の上がる中であまり距離を伸ばすのは怖いので、先週に引き続き紀見峠を越えて帰阪することにした。
明日は仕事だし、どんどん気温の上がる中であまり距離を伸ばすのは怖いので、先週に引き続き紀見峠を越えて帰阪することにした。
農閑期の日曜にだけ開業するラーメン屋がある「めのこ峠」を越えてさらに下っていく。
ついでに道すがらのWAKAYAMA800のスタンプポイントに寄れないかと思ったが、先日メカトラでたどり着けなかった丹生都比賣神社は途中まででもかなりの上りで、ここに寄って午前中に帰宅するのは難しいだろう。
息子の通学用車のトップチューブカバーなど [THUNDER]

 息子が慣れるまでと、ハンドル高を上げた「THUNDER(稲妻)」のベース車を利用した息子の通学用自転車だが、これで順風満帆かというとまた問題発生。ヒザがフレームに当たって痛いとのこと。どうやら息子も私と同じ内股ペダリングで、ヒザがトップチューブに当たりやすいようだ。
息子が慣れるまでと、ハンドル高を上げた「THUNDER(稲妻)」のベース車を利用した息子の通学用自転車だが、これで順風満帆かというとまた問題発生。ヒザがフレームに当たって痛いとのこと。どうやら息子も私と同じ内股ペダリングで、ヒザがトップチューブに当たりやすいようだ。
トップチューブがないCARACLE-Sや、トップチューブ位置が低いCARACLE-COZなら一気にペダリングが楽になるのはわかっているが、今から息子の通学用に用意するわけにもいかない。
 慣れの問題だからしばらく乗ってみろ、と言いつけたものの一応手を打つことにした。ヒザをぶつけても痛みを軽減できるように柔らかいもので覆うことを考えたが、手っ取り早いのはバーテープ。TORACLE-COZに装着した余りがあったので巻いてみることにした。
慣れの問題だからしばらく乗ってみろ、と言いつけたものの一応手を打つことにした。ヒザをぶつけても痛みを軽減できるように柔らかいもので覆うことを考えたが、手っ取り早いのはバーテープ。TORACLE-COZに装着した余りがあったので巻いてみることにした。
 ヒザが当たる位置を確かめるためにまたがってみると、ちょうどシッティングでヒザが通る近辺に折りたたみ部分の張り出しがある。「ハハン、ここが当たるのか」と出っ張りを覆うようにバーテープを巻き周囲もカバーして万全を期した(つもりだった)。
ヒザが当たる位置を確かめるためにまたがってみると、ちょうどシッティングでヒザが通る近辺に折りたたみ部分の張り出しがある。「ハハン、ここが当たるのか」と出っ張りを覆うようにバーテープを巻き周囲もカバーして万全を期した(つもりだった)。
 ついでにいくつか作業。まずバルブを虫ゴム式から、いわゆるスーパーバルブ系のものに交換。これまでの経験でいうと「10倍長持ち」というのは疑問もあるが、寿命が伸びるのは確かだし、空気入れが楽になる。
ついでにいくつか作業。まずバルブを虫ゴム式から、いわゆるスーパーバルブ系のものに交換。これまでの経験でいうと「10倍長持ち」というのは疑問もあるが、寿命が伸びるのは確かだし、空気入れが楽になる。
 続いて先日後ろに下げた前カゴを、さらに後ろに下げる試み。前カゴは少しでも後ろ(ステアリング軸に近い)方がハンドリングが安定する。ハンドルを上げて突き出しを少なくしたので、突き出しの少ないステー(画像の下側)に交換してみた。
続いて先日後ろに下げた前カゴを、さらに後ろに下げる試み。前カゴは少しでも後ろ(ステアリング軸に近い)方がハンドリングが安定する。ハンドルを上げて突き出しを少なくしたので、突き出しの少ないステー(画像の下側)に交換してみた。
 さらに後ろに下げることができたが、ブレーキレバーを支障なく握れる位置だとこの辺りが限界かなというところ。レバーが干渉しないようにアップライトハンドルに交換してもっと後ろに・・・などと、どんどんクロスバイクのスポーティーさが失われていく想像。
さらに後ろに下げることができたが、ブレーキレバーを支障なく握れる位置だとこの辺りが限界かなというところ。レバーが干渉しないようにアップライトハンドルに交換してもっと後ろに・・・などと、どんどんクロスバイクのスポーティーさが失われていく想像。
走行安定性が向上する調整はできたが、これによりライトとステーが接触してしまった。ひとまずは装着位置と角度を変えて凌いだが、いずれにしてもステーがライト前が横切る状況は好ましくない。ライトは色々悩んでいるが、前カゴがあるのでハンドル装着ライトは使用しない方が良いし、前カゴに装着できるライトやライトを装着するアダプターにあまり良いものがない。ハブ軸付近に装着するライトは、光が引き伸ばされて照射性が落ちるし、オン/オフが面倒で、張り出しているのでぶつけるリスクも高い。
息子の通学用車のハンドル高UP [THUNDER]

 「THUNDER(稲妻)」のベース車を利用した息子の通学用自転車は、一応の完成を見ていた。ところが、前傾姿勢のスポーツ車経験のない息子は「腰が痛い」といって乗りたがらない。
「THUNDER(稲妻)」のベース車を利用した息子の通学用自転車は、一応の完成を見ていた。ところが、前傾姿勢のスポーツ車経験のない息子は「腰が痛い」といって乗りたがらない。
 GW中に近所を一緒に走ってフォームを見てみたが、スポーツ車に慣れた身には、それほど強い前傾には見えない。単に慣れていないのであれば、しばらく乗って体幹が鍛えられれば痛みは消えるはず。とは言え、中学までは野球を続け、高校に入ってからはハンドボール部と体育会系の息子が乗った途端に痛がるのは、腰に慢性の故障があるのかもしれない。
GW中に近所を一緒に走ってフォームを見てみたが、スポーツ車に慣れた身には、それほど強い前傾には見えない。単に慣れていないのであれば、しばらく乗って体幹が鍛えられれば痛みは消えるはず。とは言え、中学までは野球を続け、高校に入ってからはハンドボール部と体育会系の息子が乗った途端に痛がるのは、腰に慢性の故障があるのかもしれない。
 息子の痛みの質がわからないので、無理に乗せるのは止め、まずはハンドル高を上げて楽に乗れるようにしてやることにした。
息子の痛みの質がわからないので、無理に乗せるのは止め、まずはハンドル高を上げて楽に乗れるようにしてやることにした。
 すでにステムは前上がりにして、一番高い位置にセットしているので、これ以上どうやってハンドルを上げるか?
すでにステムは前上がりにして、一番高い位置にセットしているので、これ以上どうやってハンドルを上げるか?
ライズの大きなハンドルバーに交換することも考えたが、フォークコラム(ステアリング管)を延長するエキスパンダーが一番安上がりに済むので、通販で購入した。勤務先に突き出しの少ないステムが有ったので、これも頂いてきた。
 まずは今装着されているステムを取り外す。ハンドルバークランプを外し、コラム固定ボルトも緩めて抜き取る。
まずは今装着されているステムを取り外す。ハンドルバークランプを外し、コラム固定ボルトも緩めて抜き取る。
 エキスパンダーは2箇所のコラム固定ボルトがしっかりフォークコラムを締め付ける高さになるようスペーサーを抜いて調節。
エキスパンダーは2箇所のコラム固定ボルトがしっかりフォークコラムを締め付ける高さになるようスペーサーを抜いて調節。
仕組み上、ステムは装着しなくても、引き上げボルトを締め付ければヘッドパーツは固定されるが、できるだけ高い位置に固定できるようにスペーサーを挟み、ステムを装着してから引き上げボルトを締め付けた。
一年ぶりの自己記録更新 [鍋谷峠-紀見峠]

さすが自転車月間というか、今日はツアー・オブ・ジャパン(TOJ)堺ステージの観戦イベントやシクロジャンブル、TADA集まれ、といったいくつもの自転車イベントのお誘いがあった。とはいえ、先週末はTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)が走れない状態だったし、上海出張の疲れもあってトレーニングを休んでいる。
今週末も昨日は出勤日だったので、トレーニングのチャンスは今日しかない。前後ディレーラーの交換で復活したTORACLE-COZの試走もしておきたいので、イベントは不義理をして鍋谷峠に行くことにした。
しばらく前から服部産業のH本さんにお誘いを受けていたので、ご一緒することにした。ちなみに、COZの復活に協力してくれた近所の友人は昨日からブルベ600km参加中。
6:30過ぎに自宅を出走して、近所のコンビニでH本さんと待ち合わせ。カフェイン(コーヒー)を注入して、7時前に再出走。身体がちょっと熱っぽかったが、脚はまずまず回っている。やや雲が多い目ながら晴れた空の下を和泉山脈に向かって南下していく。
 山麓の父鬼集落下の温度計は8時前ですでに20度と、すっかり初夏の気温。湿度も高めでショートスリーブジャージとレーパンでも寒さは感じない。
山麓の父鬼集落下の温度計は8時前ですでに20度と、すっかり初夏の気温。湿度も高めでショートスリーブジャージとレーパンでも寒さは感じない。
ところが、温度計の下の看板の通り、今日はリフレッシュ活動のため国道480号線旧道が規制されるよう。「国道480外」という意味がわからないし、「通行止」と明記されているわけではなく「車両等の交通規制依頼」という記載が曖昧。軽車両(自転車)まで止められるのかはわからないが、いずれにしても規制開始の9時までには上り切れるだろうと、先に進んだ。
毎度のごとく製材所前の鍋谷橋からアタック開始。序盤はペースを抑えて、というかもうひとつ脚を回せず心拍数は160bpm半ば程度。前回同様に、できるだけシッティング比率を高めてやや重めのギアを踏み込みながら上る。傾斜が急になるところもギリギリまでシッティングでしのぎ、ダンシングは最小限にするよう心がける。
H本さんは例によって斜め後ろに張り付いているので、手は抜けない。中盤からは脚も回り出し、心拍数も170bpm台に上がってきたが、175bpmを越えないように意識した。気温も湿度も高めなので、汗が吹き出しポタポタ落ちていく。
 久々に長時間170bpm台をキープしたので、苦しい。ちょっと油断すると160bpm台に落ちてしまうので、必死でペースを維持する。後半は踏み込む余裕がなくなり、腰の痛みも強くなってきたので、ダンシングの比率も高くなってきた。それでも終盤にペースを上げていき、最後は心拍数を186bpmまで上げて鍋谷峠にゴール。
久々に長時間170bpm台をキープしたので、苦しい。ちょっと油断すると160bpm台に落ちてしまうので、必死でペースを維持する。後半は踏み込む余裕がなくなり、腰の痛みも強くなってきたので、ダンシングの比率も高くなってきた。それでも終盤にペースを上げていき、最後は心拍数を186bpmまで上げて鍋谷峠にゴール。
最後は久々に苦しく、脚を緩めたくなったが、何とか踏ん張った。ゴール後はしばらく手がしびれて、荒い息が収まらなかった。
心拍数を190bpm以上にまで上げられなかったので、数値上は追い込みきれなかったとも言える。それでも、タイムはなんと25分34秒と、ほぼ1年前にCOZで初めて上った際に出した鍋谷峠の自己ベストタイムをわずか9秒ながら更新した。昨秋以来、仕事が忙しかったことや、大腿骨のチタンボルト抜取り手術などで、思うように自転車に乗れなかった。峠トレーニングもスタートが遅れたので現時点でのタイムに期待はしていなかったが、過去最高記録が出たことは良い材料だ。
年齢的にも自己ベストを更新するのは年々厳しくなっているが、CARACLE-COZとH本さんの指導のお蔭で50歳になっても記録が更新できた。前半にセーブして(全力を出せなかった)、シッティング主体で上ったことが功を奏したのかは不明だが、走りがギクシャクしていたことを自分でも感じていた。H本さんも、シッティングで引っ張りすぎて、踏めなくなってからダンシングに切り替えることで疲れが溜まっていったように見えたとのこと。現時点ではあえて「シッティング縛り」などの不効率な走りをするのもありだろうが、最終的に長い上りでは省エネ走法が一番早い。効率の良い走り方の練習もしていかなければならないだろう。 (さらに…)
TORACLE-COZ復活 [ディレイラー交換]

 先週、先週、丹生都比賣神社への上りで動かなくなったTORACLE-COZのDi2リアディレーラーRD-9070。一気にトップ側に落ちてからはそこから動かず、シフト操作をしてもモーターの唸る音が聞こえるだけ。
先週、先週、丹生都比賣神社への上りで動かなくなったTORACLE-COZのDi2リアディレーラーRD-9070。一気にトップ側に落ちてからはそこから動かず、シフト操作をしてもモーターの唸る音が聞こえるだけ。
管理ソフトE-tubeでも「異常の可能性あり」との判定が下されたが、電動ディレーラーの内部の異常は、ユーザーには手の施しようがない。シマノでもDi2ディレーラー内部の修理は難しいようだ。友人からの借り物だけに頭が痛いところだが、友人は自分も含めた使用期間と走行距離を考えると寿命だろうとの判断だった。逆に謝られてしまい、恐縮。
 自腹で直ちに用意できるわけでもなく、代替品も友人の予備を貸してもらうことになったのだが、フロントディレーラーもそろそろ寿命が近いだろうとの友人の見立て。ついては、友人宅で前後ディレーラー、そしてチェーンをまとめて交換することになった。
自腹で直ちに用意できるわけでもなく、代替品も友人の予備を貸してもらうことになったのだが、フロントディレーラーもそろそろ寿命が近いだろうとの友人の見立て。ついては、友人宅で前後ディレーラー、そしてチェーンをまとめて交換することになった。
9070シリーズはすでに供給されていない旧モデルのため、現行のR9150シリーズに変わる。まずはフロントディレーラーをFD-9070から、FD-R9150に交換。歯先のクリアランスが前後で微妙に合わないのは、元からだったのかモデルによる微妙な差なのか? FD台座の角度は調整可能なので、そのうち最適化しよう。
 リアディレーラーはRD-9070から、RD-R9150に交換。Bテンションボルトは最も緩めた状態であることを確認。
リアディレーラーはRD-9070から、RD-R9150に交換。Bテンションボルトは最も緩めた状態であることを確認。
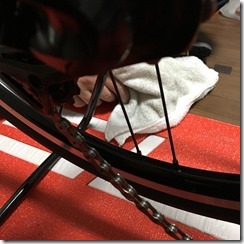 チェーン長は前後共に最大ギアに掛けてピンと張った状態にプラス1~3リンクが、シマノのマニュアルの推奨長。つまりプラス2リンクが最適長ということだ。
チェーン長は前後共に最大ギアに掛けてピンと張った状態にプラス1~3リンクが、シマノのマニュアルの推奨長。つまりプラス2リンクが最適長ということだ。
ただし、CARACLE-COZは折りたたみ自転車なので、折りたたみ時の負担を減らすためにシマノ推奨値プラス2リンクが完成車のチェーン長だ。チェーンは2リンク単位でしが長さ調整できないのでピッタリとは行かないが、合計4リンク足して長さを決定(正確にはプラス3.7~3.8リンク程度)。RD-R9150はケージ長が長くなってリア最大30Tに対応していることを考えると、もう少し長めでも良かったかもしれない。接続はシマノ純正のクイックリンクを使用したが、かなり固くてなかなか嵌らなかった。一度嵌れば逆にしっかりした固定力が期待できて安心できる。
 インデックス調整は少々手間取った。全てのギアでシフトアップ・ダウン共にスムーズに動作するポイントはかなり狭く、Di2システムとハイロー調整ボルト、Bテンションボルトの微調整を繰り返した。
インデックス調整は少々手間取った。全てのギアでシフトアップ・ダウン共にスムーズに動作するポイントはかなり狭く、Di2システムとハイロー調整ボルト、Bテンションボルトの微調整を繰り返した。
 納得の行くところまで詰めて、無事にTORACLE-COZは復活した。
納得の行くところまで詰めて、無事にTORACLE-COZは復活した。
上海出張の疲れもあって今週末はトレーニングを中止したが、来週はCOZで走り出せる。いきなり遠出は怖いので、近場で新ディレーラーを試してみよう。
ご注意:本記事は、久行の個人的趣味とテック・ワンの技術検証を兼ねて行っているもので、同様のカスタマイズに対して安全性や耐久性を保証するものではありません。安全性に問題がなく、ご要望の多いものは純正品に取り入れる可能性もあります。興味のあるパーツや加工については、ご意見をお寄せください。

