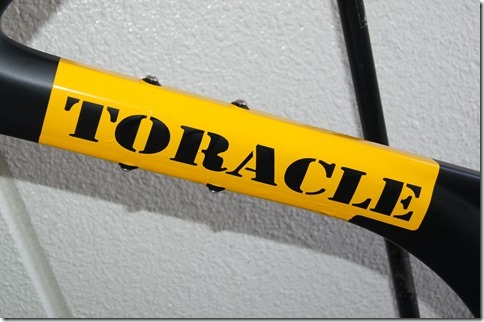GOWES Relationship Women’s Meeting in 近江八幡

本日は、仕事絡みでインドネシア人サイクリストとの交流イベント、GOWES Relationship Women’s Meeting in 近江八幡にレンタルバイクとしてCARACLE-Sを貸し出し出すことになり、私と同僚もライドに加わることになった。

幸い台風は南海上を早くに通過して、朝から台風一過の青空が広がった。貸出用と自分たち用を併せ、9台のCARACLE-Sと2台のChalet-COZを積み込んだハイエースで、近江八幡駅前にやってきた。スタッフ集合時間より30分以上早く着いてしまったので、まず自分たちの自転車の準備。私はTORACLE-S(CARACLE-S 2016試作車)で、同僚I井さんはChalet-COZ試作車。2人とも市販色と異なるフレームカラーで、仕様も特殊なのはご愛嬌。

9時前に中心スタッフのYASUさんやアケさんと合流し、駅前の受付場所に貸出用のCARACLE-Sを組み立てて並べていく。

新モデルChalet-COZも持ってきたので、YASUさんやアケさんが早速食いつく。

9時過ぎから徐々に参加者が集まり始める。自分の自転車を持参している人も多いが、特にインドネシア人女性は自分の自転車が無い参加者が多く、我々のCARACLE-Sや駅のレンタサイクル(ママチャリ)を借りて参加する。

距離は26kmと短く、完全に平坦なコースなので、シングルスピードの姿も。トップチューブとダウンチューブが双胴になった変わり種。

参加者が揃い、開会式。今回は原則女性限定のイベントで日本人よりインドネシア人の方がやや多いようだ。男性もカップルなら参加は可能で、在大阪インドネシア共和国総領事館の総領事も、夫婦で参加している。我々スタッフも男性が混じっている。
実りの秋の自転車日和 [金剛山ロープウェイ乗り場往復]

先週末は彼岸花(曼珠沙華)の盛りだったと思われたが、仕事でトレーニングライドはお休み。2週間ぶりの出走は、近所の友人とも1ヶ月ぶりの同行となった。私は相変わらず足の指の痛みが残り、友人も試験勉強で9月は全く走っていないとのこと。遠出は不安が残るので、今日は金剛山ロープウェイ乗り場まで往復することにした。

すっかり涼しくなったが、まだ防寒装備を着こむほどではなく快適な気温。6:30に近所のコンビニで待ち合わせて再出走。ひとまず府道30号線を東進し、北野田駅を過ぎた東野交差点を直進して府道を離れる。黄金色に染まった稲穂の向こうに行く手の金剛山がくっきりとそびえる美しい風景に、秋を実感。

木材団地からPLの塔(世界大平和祈念塔)のある丘を越え、富田林駅付近を過ぎて府道705号線に入る。

今日は寄り道せずに走り続け、本格的な上りが始まる森屋交差点に7:50頃到着。TORACLE-COZ 2(CARACLE-COZ DB)2回めの遠出だが、10mmハンドルポジションを下げたら力を入れやすくなった。ラージサイズ化で37mm伸びたフロントセンターのお陰で前荷重になってもハンドリングが安定しており、油圧ディスクブレーキの制動力と相まって走行時のストレスがかなり減っている。
小休止している間に何台かの自転車が過ぎていき、中にはDAHON Dash Altenaらしき小径折りたたみ車もいた。追いかけがてら、軽くアタックを開始。

序盤の急傾斜でDashに追いつき、「(同じ)ミニベロですね」と声を掛けて先行した。少し傾斜が緩むと、沿道の棚田が黄金色で美しい。しばらく友人と連れ立って走り、急傾斜で私が先行し、緩斜面で友人に抜き返される展開が続いた。

消防署の分署を過ぎて、バイパスを避けて旧道に入る。田んぼの畦には彼岸花が咲いているが、盛りを過ぎて枯れ始めている。桜並みに見頃が短いので、今年は見逃したのが残念。
TORACLE-COZ 2(ディスクブレーキ)シェイクダウン [竹内峠-穴虫峠]

この夏はとにかく暑かったので室外作業が厳しかったし、まとまった時間が確保できずになかなか組み立てられなかったCARACLE-COZ DB(ディスクブレーキ)。ようやくのことで、この連休前半の土日で概ね組み立てた(後日レポート予定)ので、シェイクダウン(試走)に出ることにした。
COZ DBは発売されたばかりだが、私が組み立てた個体は市販仕様の先を行く(全)油圧ディスクブレーキとフロントシングル仕様のコンポを搭載し、それなりの時間を掛けて使い勝手や耐久性を検証するのが目的。とはいえ、コンポ以外のパーツの多くはリムブレーキ版TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)からの移植で、しかもほぼ同じデザインで黄色のカッティングシートを貼付したので、一見すると変化に気が付かない人もいるかもしれない。名付けて『TORACLE-COZ 2』発進だ。
6:36に出走したが、数日前に足の指をぶつけてペダリングが苦しいので、遠出は厳しい、そもそも、組んだばかりの自転車はトラブルを生じやすいし、挙動に慣れていないので身体にも負担がかかる。遠出はリスキーだ。テストのために上り下りを混ぜたいので、標高の低い竹内峠を越えて奈良県の端をかすめ、穴虫峠で大阪府に帰ってくるルートを取ることにした。

先週に比べても一気に気温が下がり、走り出しは肌寒いほど。降水確率0%で、空気も乾燥して爽やかだ。富田林の丘陵地を越えて石川を渡る行く手には、これから越える二上山が正面に見える。河川敷の南河内サイクルラインには早朝から次々と自転車が過ぎていく。
フレームをMからLサイズに変え、ホイールベースが37mm伸びたことは、はっきりと走行性能の差として現れる。正直なところ、Mサイズと比べると鈍重さを感じなくもない。逆に言えば安定しているということで、幹線道路を25km/h以上で走る際などにストレスが少ない。フロントセンターが伸びて前輪荷重が減るからだと思うが、上りでもふらつきにくく、ダンシングがしやすい。悩まされていたステアリングコラム上端とヒザの接触が解消されて、窮屈な感じが無くなった。
フレーム、ハンドルバー、デュアルコントロールレバーが変わり、計算値でステム90mmを装着した。ところが実際に装着してみると、ハンドル形状とデュアルコントロールレバーの大きさの違いでブラケットポジションが約2cmも遠くなった。20mmは短いステムに交換しようと思っていたが、以前より高くなったハンドルポジションのせいか、しばらく走っているとそれほどの違和感を感じなくなってきた。
近年は近く低い位置にハンドルバーをセットして、走行中にブラケットを握っている比率が高かったが、少し手前のハンドル部を握るようすれば前傾も普段と同じ程度になる。以前は、もっぱらドロップハンドルバーの肩(左右から前後に90度方向を変える部分)を握っていたことを思えばまだまだ近い。意外とこのままでも良いかもしれないし、短くするにしてもせいぜい10mmかな、と思うようになった。
油圧ブレーキはやはり大きな違いを感じる。ストッピングパワー自体はハイブリッドディスクブレーキでも過剰だと思うが、油圧はワイヤーの摩擦抵抗が無いので、とにかく引きが軽い。リムブレーキの調子でうっかり握り込むと、すぐに後輪がロックしたり、後輪が浮いたりする。慣れの問題だろうが、繊細なタッチを心がけながら走るので、結構疲れる。これでも制動力が一段下がる140mmローターでレジンパッドなのだから、160mmローターでメタルパッドだとどうなるか怖いほどだ。
この軽いレバータッチのお陰で、指先が1本届けば強力な制動力が得られるので、ブラケットポジションが少々遠くてもさほど支障がない。

国道166号線にぶつかる六枚橋交差点から、竹内峠に向けて本格的な上りが始まる。国道を避けて旧道の竹内街道を上っていくが、強く踏み込むとやはり足の指が痛いのでのんびりペース。

近年の保全活動もあって風情のある家並みが続く竹内街道だが、傾斜は結構厳しい。もっとも、フロントシングル46T、リア最大34Tのギア比は、これまでの39x28Tより低いので意図的に落とさない限り出番はなかった。とりあえず手持ちのフロント46Tを装着しているが、トップ側のギア比が大幅に低いので48か50Tにすることも考えている。
道の駅近つ飛鳥の里太子付近で国道に合流し、引き続き上り続ける。Lサイズ化とディスクブレーキ化、そしてコンポのダウングレードによる重量増は、フロントシングル化では相殺できず、恐らく600~700g重量が増えている。カタログスペック(ペダル、アクセサリー抜き)で7.3kgはそれでも充分軽量マシンなのだが、これまでと比べればやはりやや重さを感じる。一方で前述した通り、前輪がフラつきにくく、ダンシングがしやすいので上りやすくもある。体感では功罪のどちらが上とも言い難いが、これから何本か峠を上っていけば、タイムで判断がつくだろう。

8:07に竹内峠に到着。久々に、国道が拡幅される前のルートと思われる並走路を上ってみた。切通しで掘り下げられた現ルートより一段上にある。

ここには「從是(これより)東 奈良縣管轄」の石柱が立っている。似たような奈良県の境界碑は、国道165号線に並走する旧道(長尾街道?)でも見たことがある。恐らく明治時代のものだろうが、探せば他にもあるのかもしれない。
TORACLE-COZ 2(ディスクブレーキ)組立て その2 [パーツ移植]

お盆休みに組立てを開始して、まずは油圧ディスクブレーキを装着したTORACLE-COZ 2(CARACLE-COZ ディスクブレーキ)。これまでの初代TORACLE-COZ(CARACLE-COZ リムブレーキ)から移植するパーツもあるため、中途半端で作業が中断すると、その間は遠出をする自転車が無くなってしまう。通勤用にハイレシオ化しているTORACLE-S(CARACLE-S 2016試作車)のギア比を、峠越えに使えるギア比に戻そうかとも思ったが、作業のための時間と、冷房のない室外で作業する気力をなかなか確保できず、ずるずる時間が過ぎていった。
ようやく涼しくなってきて、時間を確保できたのは1ヶ月以上経過した9月の連休。同じく先送りしていたヨメさんのママチャリのエアハブのチェックをしたり、消耗したブレーキシューを交換したり、TORACLE-Sのサドルを交換したりしてから、TORACLE-COZ 2の作業に入った。
友人に油圧ディスクブレーキの講習を受けた前回の作業でブレーキやハンドル、ステムは仮装着してある。
他のパーツ類を組み付けていく前にやっておきたかったのが、「CARACLE」から「TORACLE(虎来る號)」への変身作業。この機にデザインを見直したい気持ちもあったが、そんなことをしていたらいつになるかわからないので、初代TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB)とほぼ同じデザインのカッティングシートを用意した。
ところが、メインロゴのカッティングシートを当ててみると、Lサイズフレームはロゴ位置が少し変わっていた。CARACLEロゴを隠しきれず、最後の「E」が飛び出してしまう。ボトル台座やダウンチューブの湾曲を避ける切り欠きがあるので、貼る位置を修正することは難しい。
デザインとカットをやり直していると連休中の組み立てが難しくなるし、同色の目立たないロゴなので、貼付け作業を続行することにした。カッティングシートの接着面とフレームに中性洗剤をほんの少し垂らした水をスプレーして、位置を調整しながら貼付ける。
久々の府外脱出 [千早峠(金剛トンネル)-紀見峠]

先週はスポークテンションを上げすぎたホイールのトラブルで中途半端だったが、規定値のテンションで再調整した。リスクを減らしたホイールを装着したTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)で本日も6:40出走。
35度超えの最高気温が続く中で長時間ライドを避けてきたが、ようやく明け方の気温が少し下がってきた。日の出が遅くなって、気温上昇も遅れ気味なので、今日は久々に大阪府外脱出を目指す。体調は少しだるさがあったが、コンビニでカフェインを注入して脚が回りだした。
久々の府外脱出でいきなり難易度の高いルートは危険だが、二条山周回ルート(竹内峠-穴虫峠)は短すぎる印象だし、相変わらず通行止めの峠が多い。結局は、走り慣れた(走り飽きた?)千早峠(金剛トンネル)-紀見峠ルートで走ることにした。コロナの移動制限が解除された後、6/20にも走ったコースだ。
河内長野駅に向かって国道310号線を走っていると、アップダウンのピークから、青空の下に金剛山系の山並みがくっきり。早朝の気温の低さが秋を感じさせ、気持ちがいい。
河内長野駅裏手の諸越橋で石川を渡って、千早峠(金剛トンネル)を上り始める。
観心寺付近の温度計は23度を表示。やはり汗は吹き出してくるが、久々の20度台前半はかなり快適だ。
久々の遠出だしのんびりと上ろう、と思っていたがロードバイクにスパッと抜かれると、少し悔しい。
(さらに…)